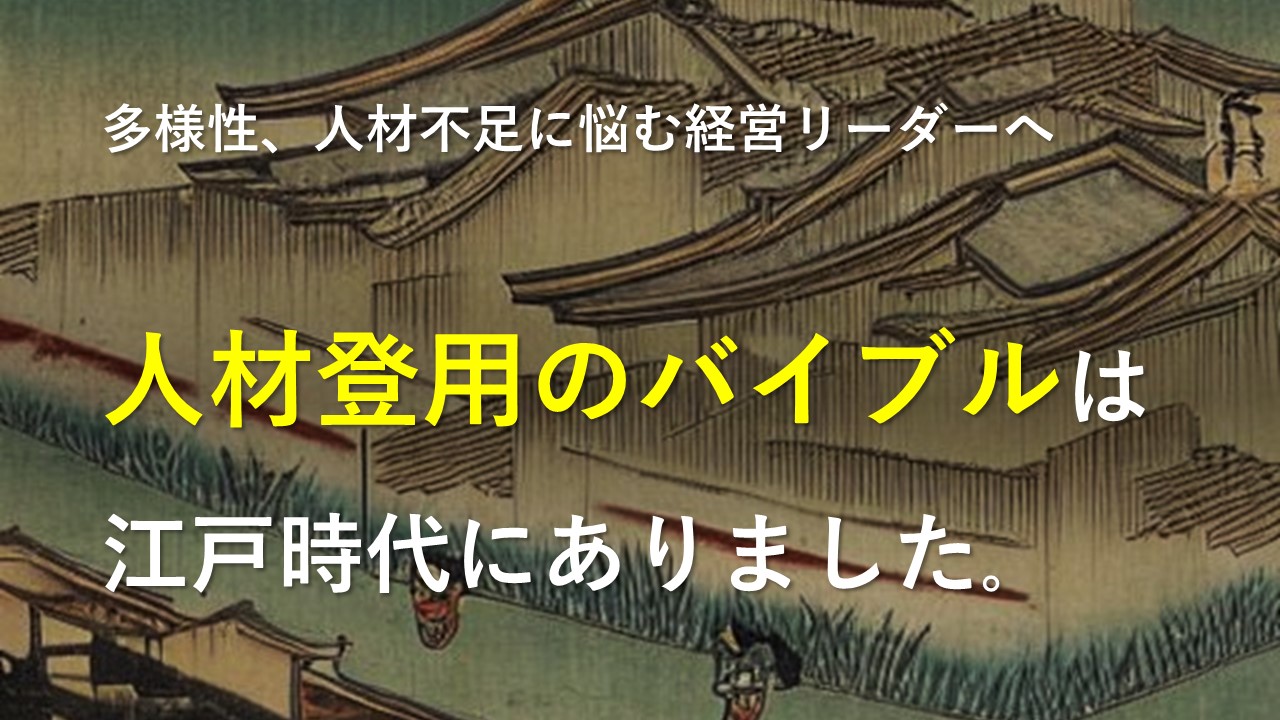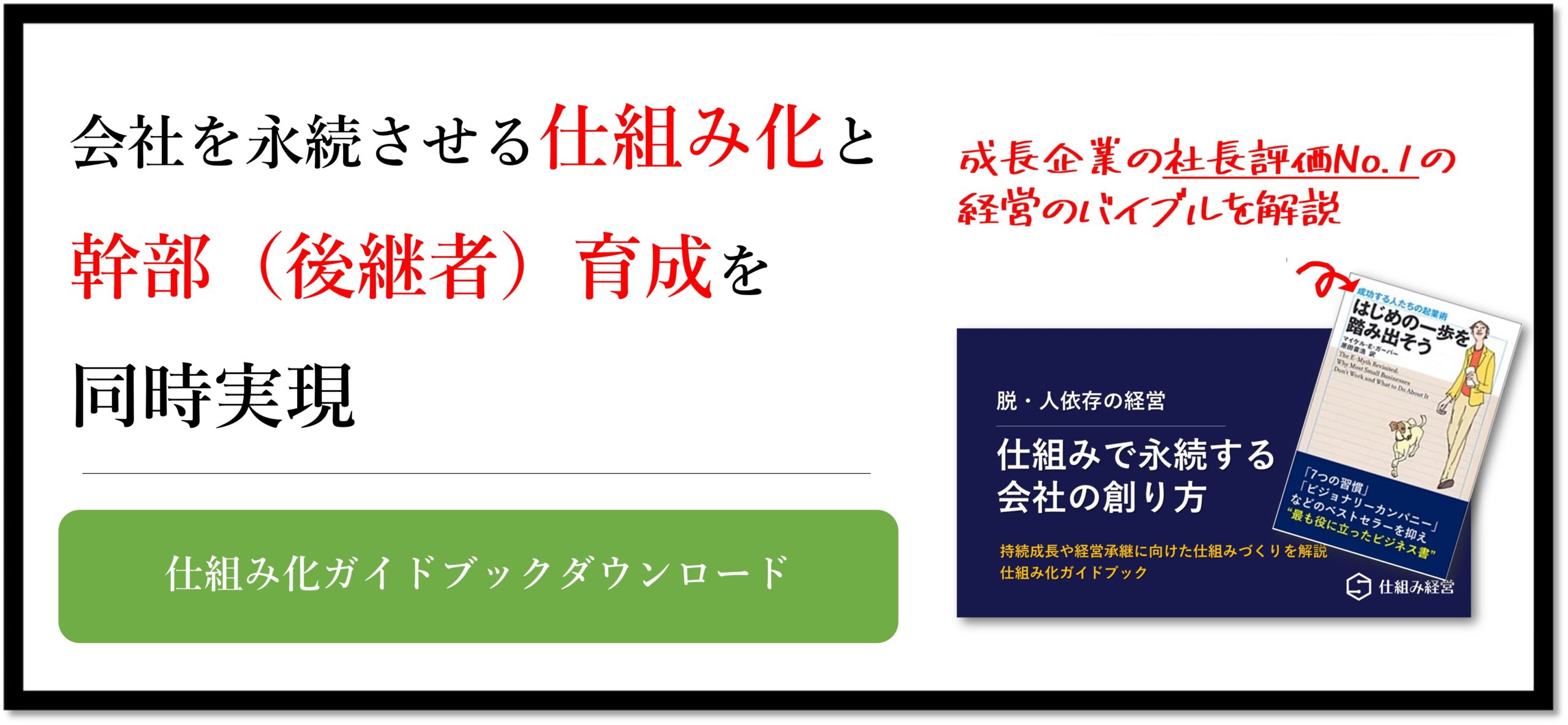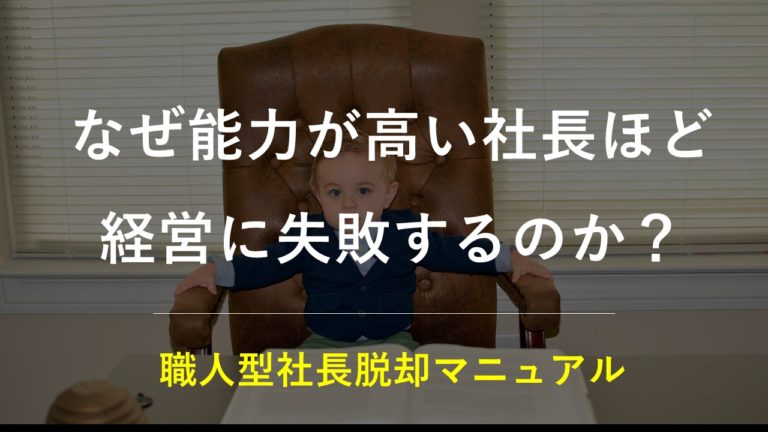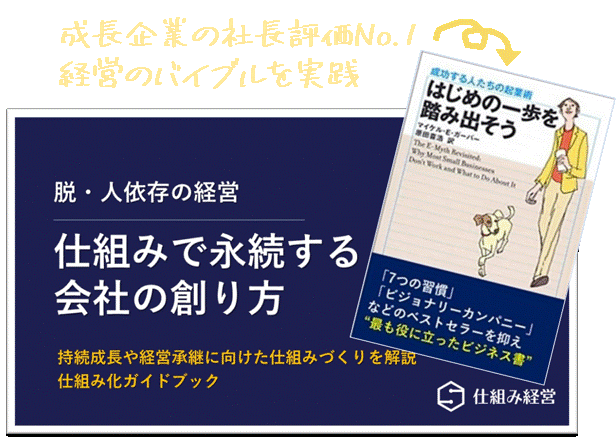そもそも人材登用の意味とは?
人材登用とは、組織内の優秀な人材を見つけ、彼らの能力を最大限に活用するために、適切な役職や職務に配置することを指します。
これは、組織の成長と発展にとって極めて重要なプロセスであり、その成功は組織の長期的な成功に直結します。
なぜいま人材登用が必要とされているか?
多様な背景を持つ人々が集まることで、新たな視点やアイデアが生まれ、組織の創造性や革新性が向上します。いわゆる多様性です。そこで人材登用の仕組みを考えることが大切になってきます。これまで経営層や幹部層に居なかったような人材を見つけ出し、重要なポストに付けることで、多様性が生まれます。
また、人材不足の問題があります。労働力人口が減少し、外部から優秀な人材を確保することが難しくなっています。そこで、改めて自社の組織内を見渡し、すべての人材の可能性を吟味し、才知ある人を登用することが有効になってきます。
人材登用は江戸時代の享保の改革(徳川吉宗)に学べ

日本には参考とすべき、人材登用の事例があります。それが江戸時代の8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革です。徳川吉宗は前代の奢侈に流れる風潮を押え、 倹約を奨励し、幕府の改革を行いました。たとえば、質素倹約の励行、 目安箱の設置、公事方御定書の設定、足高の制、上米の制、相対済令、 定免法の採用、新田の開発、甘藷(かんしょ)などの新作物栽培の奨励などです。
このうち、足高の制というのが今でいう人材登用の仕組みに当たります。
足高の制とは?
人材登用のバイブル「政談」
ドラッカーよりはるかに早く原則に気が付いていた
人材登用は天地自然の理に従え
では以下から荻生徂徠の「政談」をもとに人材登用の秘訣を見ていきましょう。
人材の新陳代謝は自然の理
天地自然の摂理に従えば、古いものは次第に消え失せ、新しいものが生まれてくるのが当然のことです。すべての存在はこの法則に従っています。古いものを永遠に保持し続けることは不可能であり、木材は朽ち果て、五穀は毎年新たに実り、人間も老いていくことで新たな世代が交代していきます。また、天地の摂理によれば、下から上へと昇っていき、昇りつめたものは次第に消えていき、新たなものが代わって現れるのも自然なことです。
しかし、政治の世界では、古くから功績のある家や人を特別に大切にし、その家が存続するよう願うことが一般的です。家族の中でも、曽祖父母や祖父母、そして両親の寿命ができるだけ長く続くよう祈るのは、人間の情に基づく普遍的な感情です。しかしながら、天地の摂理と人間の情は必ずしも一致しません。いくら保存しようとしても、古いものはいずれ消え失せていくものです。また、古いものが早く消えればよいというのは過度に冷徹な考え方であり、聖人の道には合致しません。同様に、古いものを執拗に保存し続けることも愚かな考え方であり、やがて新たな才知ある者が登場して政権を変えるでしょう。
聖人の道は、人情の常に敬意を払いつつも、感情と矛盾しないようにし、物事の理を冷静に理解して行動することです。単に人情に囚われることもなければ、物事の理だけを追求することもありません。世の中の人々を取り扱う方法の基準は、このバランスにあります。
かつて古代中国においても、堯・舜・禹などの聖人や湯王・文王・武王の子孫たちも消え失せ、後継者を持たなくなりました。日本でも源頼や足利尊氏の子孫たちは存在しなくなりました。名家も断絶してしまい、現在の大名たちは昔は身分の低い人々から軍功によって昇進した者たちです。大名であっても正統な血統を持つ家系は希少であり、血統が絶えると養子を迎えることが多いのも事実です。それでも、上は上、下は下と厳格な家系を維持しようとするのは、時に天地の摂理に背くこととなります。上位の者に才知がなくなれば、世の末になり乱世が生じ、下位の者の中から才知ある者が台頭し政権を変えることでしょう。
下から才知ある人を下から登用せよ
聖人はこの摂理を深く理解されています。政権が長く続くようにと、賞罰の制度を定め、才知ある下の者を選抜して昇進させ、一方で上の身分の者で血統が絶えたり悪事を働く者は、自然の力に委ねて滅亡させます。これにより、賢者は常に上に位置し、愚かな者は常に下にとどまることとなります。このような調和があれば、天地の摂理に合致し、政権を長く維持することが可能です。この兼合いを理解しないと、天・地・人の全体の摂理に適合しないことになり、天意に反する政治となってしまいます。そのようなことを理解しましょう。
また『易経』にも「下より升る」という記述がありますが、これは単なる抽象的な理法の説明だけではありません。一年の間にも、春と夏には天の気が下に降り、地の気が上に昇り、天地の調和によって万物が生長します。秋や冬になると、天の気は上に昇り、地の気は下に降り、天地の調和がなくなり、万物が衰えてしまいます。人間社会も同様です。才知ある者が下から昇進して重要な役職に就く場合、君主の心が下々まで行き渡り、まるで天の気が下に降りるようです。才知ある者が下から昇進することで、下の情勢をよく理解する人が上に昇ることになり、下々の苦しみや世の中の状況が上の方によく知られ、まるで地の気が上に昇るようです。
これにより上下の間に断絶がなくなり、意思が円滑に伝わるため、天と地の調和と同じように国家が良く治まり、春夏のように世の中が豊かに繁栄します。反対に、下の才知ある者を選抜しない場合、君主の心が下々まで行き渡らず、まるで天の気が下に降らないようです。それでは能力のある者が下から昇進することがなくなり、下の情勢が上の方に伝わらず、まるで地の気が上に昇って行かないようです。上と下の間が断絶し、意思が伝わらないため、天と地の調和がなくなり、国家が衰えるのは、秋冬のように万物が枯れ失せるかのようです。
いままで組織の下層部にいた人が登用されることで、上層部と下層部の断裂が無くなると言っています。これもとても大事な指摘ですね。
平和が続けば、上層部は無能になる
太平の世が長く続くと、能力ある人は下に位置し、上層の身分の人々は愚かになってしまいます。その理由は、人の才知はさまざまな困難や苦難を経験することでのみ育まれるからです。
人間の体は使用する部分が鍛えられて発達するもので、手を使えば腕が強くなり、足を使えば足が強くなります。弓や鉄砲の狙いをつけることを熟練させれば、目が鋭くなり、心を鍛えれば才知が生まれるのです。したがって、さまざまな困難や苦難を経ることで、才知が豊かに発展するのは自然の法則です。
『孟子』にも、「天が人に大きな任務を課そうとするならば、まずさまざまな苦しみを経験させる」と述べられています。このような経験をした才知は、下々の事情によく通じ、政治に大いに役立つのです。そのため聖人の教えにも、「賢才を登用せよ」とあり、下から人材を起用することが強調されています。
歴史上の例を挙げても、賢才の人々は低い身分から登場し、世襲の高位の家からは滅多に出現しないことがわかります。高位の家の子孫たちは世襲によって高禄や高官の地位に就いていますが、その先祖たちは戦国の時代に戦場で苦労し、困難を経て才知が発展してきた結果です。しかし、子孫たちは世襲で高位にあり、苦労せずに生まれ育っているため、才知が発展することは難しいのです。
彼らは下々の事情に疎く、家来たちから誤った教えを受けて成長しているため、知恵もありません。わずかな知識に誇りを持ち、生まれつきの地位によって人々から尊敬されていると思い込んでおり、主君の恩に感謝する気持ちもありません。自己中心的になり、下々の者を見下すのは自然の人間の心情ですが、これらの考え方から抜け出すことは困難です。
たとえ才知のある人がいても、下々との距離が遠いため、下情に気が付かず、ただ上層の者や目下の者に対して礼儀正しく振る舞うことに長けているだけで、下々の事情に通じた才知は発展しないため、下々の者が非常に愚かに見え、ますます自分の聡明さを自慢するような気持ちになるのです。
このような人情は古代も今も変わりません。聖人の教えでは、賢才を下から登用することを第一に考え、家系によって世襲させることは避けるように深く戒めています。もっとも、人情によって見慣れたことに安心するものであり、人々から尊敬された家柄の人々を高い地位につけると、下々の者の心にもそれが当然と思われて命令がよく守られることもあるでしょう。
『孟子』には、「賤しい身分の人を取り立てて尊貴な人の上に置いたり、もと君主と疎遠であった人と懇意にして、もとから親しい人よりも寵愛したりするようなことは、軽率にしてはならない」という趣意の言葉がありますが、これは人材登用に際して人情に逆らわないようにとの注意であって、賢才を登用するのが聖賢の教えに合致した道の法則であることを知っておくべきです。
私たちは、経営リーダーは現場の仕事をしてはいけない、お伝えしています。現場の仕事は現場の人の仕事であり、社長には社長の仕事があるかです。しかし、だからと言って、経営リーダーが現場の人の事情を知らなくていいわけではありません。これを下事と下情の違いと言います。リーダーは下事をする必要はないが、下情を知る必要があるのです。徂徠がここで言っていることもそれに当てはまると思います。
部下の意見を聞けば良いわけではない。
しかし、現代の利口な人々の考えは、「たとえ道理がそうであっても、上に立っている人々をみな下へ追い落として、下の階層から立身させ、上と下をひっくり返すことは不可能でしょう。もし実行できたとしても、上に立っている人々はそのままにしておき、下の者から提案される意見を聞いて採用させるようにすれば、聖人が賢才を登用せよと言われたのと同じ道理になりますよね」と主張されることもあります。
しかしこれは、聖人の教えに似せた悪知恵であり、実際には何の役にも立ちません。下の者に意見を述べさせても、それを採用する側がやはり下のことを知らない人であるため、賢才の意見がうまく受け取られないことがあります。また、賢才であっても、低い地位にいたときの考えは、本気で政治に取り組まないときの考えであり、上に登用されてからの考えとは異なることがあります。上に登用されて役職に就くと、立場が変わるため、思考力も格段に発揮されるのです。古代の聖人も賢才を登用せよと説かれましたが、このような小ざかしいことをおっしゃっていたわけではないのです。
そのうえ、賢才を登用するとは言っても、今まで上に立っていた人々をすべて下へ追い落として、上と下を入れ替えるわけではありません。たとえ二、三人でも、あるいは一人か二人でも、下から賢才を登用してやれば、これまで家柄だけを重んじてきた風習が破られ、人々の視野が変わり、励みを得ることができます。そして、登用された賢才と同様の気風になる人々が増えることで、世の中が新たな活力に満ち、良い方向へ向かうことができるのです。『論語』にも、「舜が多くの臣下の中から賢い人を選び、湯王が多くの臣下の中から伊丹を選ぶと、悪人は臣下の中にいなくなった」とあります。賢才を登用するとは言っても、上と下を全部入れ替えるのではなく、重要な役職にたった一人でも二人でも起用することで、その勢いによって他の者もよい人間になるということです。
これが人君が持つ賞罰の権限です。善人に褒賞を与え、悪人に処罰するというだけではありません。一人に褒賞を与えることで、多くの人々が喜び、一人を処罰すれば多くの人々が畏怖します。その結果、世の中が生き生きとし、人々の心に勇気が湧き、世の風俗も君主の意向通りに改善されるのです。人並みに優れた賢才と悪い人間とは特別ですが、その他の人々は同じような存在であり、上に立った人の導きによって、世の中の風習に従って変化するものです。
これも鋭い指摘です。いくら部下の意見を吸い上げる仕組みを持っていたとしても、それを聞き、活用する上層部が無能であれば、何の意味もないのです。
人の心と組織が停滞する理由
近年の太平が長く続いて、世の中の変化が少なく、家柄が固定化され、幕臣の家でも上級から中級・下級までの立身の限界が決まっているため、人々の心に励みがなくなってしまいました。立身しようとするよりも、失敗を避けて安定を求める考えが広まり、世渡りをする気持ちになり、人々の心が怠惰になっているのです。これは、人を生かして使うという姿勢の結果です。同じ人でも、生かして使うか、殺して使うかによって、人間の性格が大きく変わるものです。
将軍綱吉公の御代では、旗本の家柄の良い者を側近として使うと、誰も精を出して奉公する気持ちがなくなりました。これは、家柄が定まり、人々の心が重くなっていたためです。一方、身分の低い能役者などを任用すると、低い身分からの登用が有難く思われ、褒賞に喜ばれることが多かったため、彼らはよく働き、将軍様のお気に入りとなる者も多く、立身する機会が生まれました。しかし、現在は幕府の方針が変わっているため、頑張った者が必ずしも報いられていないこともあります。それでも、下から人材を登用し使役すれば、人々は精を出し、身を入れて勤めるのが人情です。
現代の世の中では、家柄が固定化しており、旗本の平士までが家柄を厳格に守り、同格の旗本の家に養子に行こうと考え、高い役職になることを考えることすらなくなりました。身を入れて頑張っても、生涯で到達できないと思われるため、思い切って何かをしようとする意欲が失われ、安全を求めて金銭を取って養子になったり、嫁を迎えたりする悪い風習が広がっています。これらの事象も、人々の心が沈滞している結果なのです。
頑張っても自分の地位が上がることはない、と社員が考えていれば、社員は挑戦しなくなり、組織は停滞します。これは特に高齢化が進む日本の会社では考えないといけないテーマだと思います。組織の上が詰まっていれば、若手は自分の出世の道はない、と考えてしまいますからね。
出自で差別するな
綱吉公の御代に登用された能役者出身の者などは、旗本の籍から削り捨てると考える人もいますが、下賤な身分から出た人々には、貴人よりも才知がある場合があります。ただし、その才知が適切に使われないことで、問題が生じているのです。適切に活用すれば、優れた能力を持つ人々が出てくるでしょう。
さらに、彼らは将軍様のご指名によって登用されたのですから、彼らの家には何の非もないのです。金銭によって旗本になる百姓や町人とは全く異なるものです。一度旗本に取り立てられたならば、もとからの旗本と同等の待遇を受けるべきです。もしも、もとからの家柄が悪いからと軽んじるならば、将軍様の威光が傷つくことになり、好ましくありません。百姓や町人であっても、才知のある者を新たに登用して御家人にすることは、将軍様の威光による立身の道として全く問題ありません。家柄を重視する方針と、賢才を登用することは、完全に対立しており、国家の安定と混乱を左右する要素となっています。
出自で差別することの無いように、と再度述べられています。
社長の威を借りる者をのさばらせるな
役職や御徒は、将軍のお馬の近くを警護する重要な役割を果たすということが忘れられてしまい、頭の者は組員を自分の下僕のように扱ってしまうことが発生しています。
近年では、旗本たちに対する上位の者たちの態度が悪化しているとも言われています。下から出た意見に対して道理を認めてやる姿勢が不足しており、お役人たちは将軍様の威光を借りて、下の者たちを抑えつけることを好んでいます。将軍様の威光とはいえ、実際には重要な地位にある役人たちが高慢になり、自らの権威を強調するために将軍様の威光を借りるだけであります。
下の者の廉恥の心を養うというのは、古代からの道であり、下の者が恥ずかしい目に合わせないようにすることであります。旗本たちを牢屋に入れて訊問するようなことは昔はなかったのに、近年は頻繁に行われていると聞かれます。人というものは扱い方で善くも悪くもなるものです。下等な人間として扱えば、そのような人間になるということを理解しないため、このようなことが起こっているのです。これらの問題は、家柄が固定化した結果、自然に世の中の風習に従うようになったものと言えるでしょう。
旗本の次男や三男を、御徒・勘定・右筆などの職に就かせることを私が主張するのは、家柄に対して低い役職に就かせることを意図しているわけではありません。むしろ、今の家柄が固定化した風習を打破するためです。重要なのは、彼らに働く機会を与えて、その中から才知が光る者を選び取り、賞罰をもって人材を育てていただきたいということです。少々取立てに失敗したとしても、それを気にすることなく、どんな身分の者でも器量次第で高官・高禄に昇る可能性を持つ世の中を実現したいのです。今のように家柄が固定していると、中より以下の身分の人々は立身の希望を持つことが難しくなります。主君との間に大きな隔たりがあるため、下の者たちは行状も気風も低くなり、彼らの才知も活かされない可能性が高まるでしょう。
社長の威を借りて上にのさばる人たちが問題である、と指摘しています。
登用すべき人材を見極めるには?
では、登用すべき人材を見極めるにはどうすればいいでしょうか。続きを見ていきましょう。
諸役人には器量ある者を選ぶべきこと
現代において、諸役人の中に本当に器量(才能や徳性)のある人材が見当たりません。この状況は国家を運営する際に大いに懸念すべき事態です。一般的に、政策や制度のことを法とし、それを実際に取り扱う人々を人として考えます。人さえ適切であれば、政策が完璧でなくても、才能ある人々が適切に処理し、国をうまく治めることができます。しかし、人材がいない場合は、どれだけ優れた政策を立案しても、未熟な人々が取り扱うため、その政策は失敗することになります。小さなミスも大きな問題に発展し、最初に立てた政策は何の役にも立たなくなるでしょう。
そのため、国を治める上では、何よりも人材を見極めることが重要です。これは、古代から聖人たちが実践してきた方法です。
ただ、人材を見極めることは容易ではありません。一瞬で人の器量が分かるわけではありません。名将がたった一度見ただけで器量ある人を見分けるという考えもありますが、それは占いや神通力に頼らざるを得ない場合もあるでしょう。その理由は、人に向かって、「あなたの器量はどういう方面に得意であるのか。例えば侍大将になった場合、昔、甲州で武将として有名な馬場美濃守のような器量か、、山県三郎兵衛のような器量か、それとも高坂弾正左衛門のような器量か。あるいは中国の漢代における李広のような器量か、程不詳のような器量か」と尋ねた場合、その人が自分自身の器量を正確に判断するのは難しいでしょう。自分自身にさえわからないことを、他人が見極めるのは困難です。
名将が器量を見抜くためには、戦場で軍功を立てたり、人々を多く見たりして、大体の特徴を覚えています。それによって人を見分けるのですが、古い時代の大将でさえ、時には人を誤って評価して失敗することがあります。覚えている特徴に基づいては見抜けるかもしれませんが、一度も見たことのない特徴については見極めが難しいのです。
したがって、人材を見極めるには、やはり実際にその人を使ってみることが必要です。自分の眼識だけで判断しようとすれば、最終的には自分の好みの人を器量あると思い込むことになりますが、これは非常に愚かなことです。なぜなら、上に立つ者はもともと高い身分で生まれ、快適な生活を送っているため、難儀や苦労を経験したことがなく、すべてが順調だと思い込んでいるからです。
徂徠は、人を見極める唯一の方法は、実際にやらせてみることだと言っています。現代において、性格診断や面接の方法が進化した問いは言え、これは同じように当てはまるのではないでしょうか。
才知ある人を取り上げられない理由
人の知恵というものは、さまざまな難儀や苦労を経験することによって発達するものです。乱世の名将たちは、生死をかけた戦場を体験し、さまざまな困難に立ち向かったことで、豊かな知恵を身につけたのでしょう。
高い地位にいるものは、下々の者とははるかに隔絶しています。そのため、下情に通じることができず、日常の交流相手は、ほとんどが高位で高禄の人々です。高い地位の人々は、高い地位に相応しい態度を身につけており、物事の物言いや行動も上位の身分とよく合っています。それによって、彼ら自身が立派に見えるのです。対照的に、下々の者は高位の人々と交際することがないため、行動や物言いが下手くそになりがちです。また、身分が低い者は、上位の人々の性格や好みについてもあまり知りません。したがって、身分が高い者から見ると、身分の低い者が急に現れても、彼らは蔑みの気持ちを抱いてしまうことがあります。
世の中では、富貴な人を良い人と思い、貧賤な人を悪い人だと見ることがあります。ちなみに、女の子を供にしている人でさえ、蔑みの気持ちを持つことがあるものです。身分が高い人は別の考え方を持っていることを示しています。世の中では家柄が固定されているため、上を向く者も下を見る者もいます。
さらに、臣下たる者は立身を好む利欲の心を持つのは、人情として避けられないことです。誰もが主君のご機嫌に調子を合わせ、主君に気に入られようと努力します。どんな名将であっても、下の者は主君の好みの性質を見抜くため、懸命に努力し、常に機会を窺っています。そのため、主君の好みを見抜かれないということは考えられません。これもまた、人情に避けられない部分です。
いつも同じようなメンバーで集まっていると同質化が進み、本当に自分たちに必要な人材を登用することが出来ない、と言っています。これはまさに硬直化された企業文化の会社で指摘されることです。江戸時代にこんなことまで洞察していたことに本当に驚かされます。
登用した人材をどう活躍させるか
では実際に登用した人材を活躍させるにはどうすればいいでしょうか。続きを見ていきましょう。
あれこれ指示するな
上述のようなさまざまな理由から、自分の眼識や才知に頼って、人の器量を見極めようとすれば、必ず失敗することが明白です。したがって、人の器量を見極めるためには、人を実際に使ってみて、その器量を判別するのが正しい方法です。ただし、人を使うという際にも、さまざまなやり方があります。
上に立つ者が、自分の好みにより、こうせよ、ああせよと指図を与えるのではなく、その人の考えに任せて、思うままにやらせてみることが大切だと思います。末の世では、利を重んじる大将ほど指図をして人を使うことを好み、その指図に従う者を自分と心が通じる者だと思い込んで寵愛する傾向が見受けられます。しかしそのような使い方は、自己中心的で巧妙な人や佞巧(巧言令色の人)のような者を生み出す可能性があります。本当の人材を見極めるためには、こうした自己の好みに偏らず、客観的に人を評価し、実際にその人の能力を活かすことが重要です。
いわゆるマイクロメントの問題点を指摘しています。自分の手足のように部下を使うのであれば、その部下を使いこなせていると言えない、というわけです。
和して同ぜず
私たち人間は皆異なる器量や才知を持っており、まったく同じ人間というのは天地の間に存在しないものとされています。ですから、上の人の考えと完全に一致させようとせず、主君の心をよく理解し、主君の分身として尽くすことが大切です。その際、へつらったりおもねったりするのではなく、自分の本来の器量や才知を大切にしつつ、主君の考えと調和するよう努めることが真の忠誠心だと思います。仕事に対して情熱を持ち、誠実に取り組む姿勢が重要であり、そうした行動こそが大切な価値を生み出すのです。
孔子の「君子は和して同せず、小人は同して和せす」という教えにも共感します。和するとは、甘・酸・塩・苦・辛の五つの味を調和させるようなものであり、各人が異なる才知を持つことが自然なことです。上司やリーダーはどれほどの才知を持っていても、全ての分野に通じることは難しいです。ですから、様々な異なる才知を持つメンバーを集めることが、組織やチームの強みにつながるのです。一方で、同じだけの味が混ざり合ったとしても、味は単調になり、価値あるものにはなりません。私たちの組織には多様な才能が揃っており、その個々の能力を生かすことで、より豊かな結果を生み出すことができると考えています。
人の生まれつきの素質は多様であり、才知の働く方面も人それぞれです。そのため、特定の事務に適合した人材を完璧に見つけることは難しいでしょうし、誰しもが失敗をすることは避けられないことです。ですが、少しの失敗にこだわるのではなく、大きな成果を挙げることを優先することが大切です。失敗を恐れずに新たなチャレンジをすることで、成長し、組織や社会に貢献できると信じています。私たちの組織は、時代に応じた素晴らしい人材が数多く存在することを信じています。どんな時代にも、新しい価値を創造できる人材が必ずいます。
「君子は和して同せず、小人は同して和せす」は有名な言葉ですね。部下と上司のあるべき関係性について説いています。
報われなかった才知を引き立てよ
歴史上の各時代に目を向けると、亡びた王朝の時代には、器量ある人物が見当たらなかったかのように思われますね。しかし、新しい時代を築き、天下を取った側の人々も、やはりその滅びた王朝の時代に生きていた人たちでした。彼らは天から舞い降りたわけでも、外国からの移民でもありません。ただ、その時代に生き、育んだ人々が、新たな時代を創造したのです。
問題は、その時代においても器量豊かな人々がいたとしても、彼らの能力を認めず、登用しなかったことです。愚かな人々が選ばれてしまった結果、王朝は滅びてしまったのでしょう。一方、王朝を滅ぼした側では、以前に活用されなかった人材の器量を認めて登用したため、天下を統治することができたのです。
時代が変わっても、優れた器量を持つ人々は必ず存在します。ただ、彼らが社会の上層にいるか下層にいるかの違いがあります。器量ある人物が上位にいれば、優れた人材があると評価され、下位にいる場合には人材が不足していると言われるのです。しかしこのような下位にいる器量豊かな人々がいるのは、支配者側が人材を選び抜こうとする心がないからかもしれません。
たとえ人材を選びたいと思っていても、選び方が悪ければ、結局は同じ結果になってしまうのです。支配者の好みに合わせて人を選ぼうとするため、優れた知恵を持つ人々は用いられず、主君と気が合う者ばかりが登用される。結果として、選ばれた人々はただの主君の分身のような存在となり、同じような人物ばかりが配置されるのです。これでは本当の人材が育ちにくくなります。
それに加えて、さまざまな悪弊が存在し、善良な人々が認められない状況が生まれています。本来、善人として活躍できる素質を持つ人々も、悪い環境の中で育まれてしまい、ますます優れた人材が不足してしまうのです。これらの悪弊は、人々が自らの能力を存分に発揮することを妨げている最大の要因なのでしょう。
これは事業承継をした後の会社に良く当てはまるかもしれません。先代社長や前オーナーの時代には埋もれていた人材であっても、活躍の場を与えたり、適材適所を考えれば、思いがけない活躍をしてくれるかもしれません。
部下の心を捉えよ
すべての階層で、物事を率直に伝えることは非常に大切です。中には、中立的に意見を述べることができる人もいます。また、主君のために真剣に職務を考えて意見を提出する者もいます。時には主君に賞められたことで意見を出すこともありますが、意見を述べた後は、夜中に目を覚まして、「今日の意見は役に立たなかったのではないか? 御老中やお頭に気に入られず、今後の身の上に影響があるかもしれない」と後悔することもあるのが人間の心情です。こうして後悔の念がつきまとううちに、やがて物を言わないようになってしまうことがあります。
飯田覚兵衛という武功の者は、加藤清正の家来でした。彼の話によれば、「自分の一生は、清正にだまされたようなものだった。最初に武功を立てた時、戦場を離れると同僚たちは鉄砲や矢に当たって死んでいた。『もうこれ以上、武士の本業はやめよう』と思ったが、帰ると清正はすぐに『君の働きは素晴らしかった』と褒め、刀を褒美にくれた。それに引き寄せられてまた働くことになる。後悔したことは何度もあったが、清正はいつも巧みに機を失さず、賞状を与えたり、同僚たちに嫉妬されるような特別な扱いをしたため、やめることができなかった。軍配を手に持って侍大将の地位まで登りつめたのも、結局は清正にだまされて働かされた結果だ」とのことでした。加藤家が没落した後、彼は京都に隠棲し、武家奉公を辞めて安らかに暮らしたと、当時の人々から聞いています。
平和な時代でも、下の者が上層の者に物を言うことは、虎の巣に飛び込むような覚悟が必要です。このような気持ちは、下の立場にいる人々が体験しなければ理解できないものです。このことを兵書の『三略』では、「主将たる者は、部下の英雄たちの心をとらえることに努力する」と言っています。北条早雲は七種の兵書について講義を聞こうとしたが、最初の一つを聞いて「これで十分だ、他の講義はいらない」と言って、後の講義を聞かなかったといわれます。これは早雲が理解力にすぐれ、人を使い、人を見分ける方法を会得していたためです。
したがって、下から出された意見が道理に当たっている場合、少し足りない点があっても構わず、賞めてやるべきです。愚かな人は度量が狭く、下の者と競争しようとするため、「それくらいのことは誰にでもわかっている」と言って、下の者と知恵比べをしようとしますが、名将はそうではありません。名将は「下の者でありながら、そんな意見を出したのは素晴らしい」と言い、賞めるのです。このような態度で下に接すれば、下の者の心に励みが湧き、賤しい身分の者の意見も真剣に聞き届けてくれるようになります。その結果、下の者も思い切って意見を出すことができ、職務に対する意欲が高まることでしょう。しかし、少し学問をしても聖賢の教えをよく理解していない者は、下の者の意見が少しでも間違っていると、すぐに上から教え込み、その意見を半ば認め、半ば押えつけようとしますが、これは好ましくありません。
飯田覚兵衛は、加藤清正にだまされると知りつつも、忠を尽くしました。現代の経営の神様と言えば、故・稲盛和夫氏は部下に惚れられなくてはならない、という主旨の言葉をおっしゃっていますが、飯田覚兵衛も清正に惚れていたともいえるでしょう。
部下の意見の引き出し方
また、「下の者に意見を述べさせると、上下の区別がなくなる」と考える人もいますが、これは全く誤った考え方です。幕府の政務に関することは、将軍様の私事ではなく、私たちに命ぜられた職務です。老中や番頭も、将軍様から命ぜられた職務を担っています。下の地位の者であっても、政務に関する意見を申し立てる場合には、そのことに関しては将軍様と同じ立場にいます。老中や諸役人たちも、その点では同役ですから、下の者は遠慮する必要はありません。
しかし、下の者の心の浅ましさから、上のご威光に押えられて、意見を言いにくいというのが人情です。だからこそ、上の者の側から意見を引き出すように努めるべきであり、逆に下の者に物を言わせないようにするのは、天道に対して恐れ多いことです。さらに、人を使う道を知らないことにもなってしまいます。人を見極めることは、老中や番頭以上の立場にある者にとっては、第一に重要な職務です。そのことを理解していなければ、職務を果たさずに俸禄をもらっている罪に問われるかもしれません。
この職務を知っているだけでなく、ただ自分の才知を発揮するばかりを職務と考えるのは誤りです。上の者が才知を発揮すれば、下の者の才知は出ないものです。上の者が下の者と才知を競おうとするのは、上の者が若輩で未熟だからでしょう。上の者が自分の意見を抑えて、下の者を立ててやるのは、上の者に知恵がないからではありません。すべての重要なことに才知を発揮するのは役人の職務であり、大臣という立場にある者の職務ではないのです。
大臣の職とは、『大学』に引用された『書経』の秦誓篇の語に、
「仮にここに一人の臣がいるとすると、一途で真面目だが特別な技能はない、だがその心は穏やかで落ち着いており寛容である。その人を容れる度量は非常に大きい。他人の技能があると、自分もその技能を慕って持っているようにしようと努力し、他人の美しさや物事に精通した徳を見ると、それを好むのである」
と説かれています。これは、むやみに温和な人柄であればよい、という意味ではなく、人を使う道をよく理解し、才知のある人を選び出すことが大臣の職務であるからです。人の意見を聞き、道理のある点は受け入れてやることが大切です。これが、人を選び出すことが良いことだとされているのです。自分の才知を発揮して下の者と競争しようとするのは、非生産的な行為です。
上に立つ人は得意な方面があるかもしれませんが、それにこだわりすぎることは好ましくありません。得意な方面には熟達しているため、他の意見をあまり聞き入れることがないでしょう。だから「他の技なし」というのです。
前述の通り、下から申し出た意見が理にかなっている場合は、不十分な点があっても、その妥当な部分を賞賛し、適切な時機を見計らって「先日のあなたの意見は正しいですね。ただ、この点で行き詰まっていますね。どうすれば改善できると思いますか」と伝えるべきです。このアプローチにより、下の者は自分の意見が評価されていると感じ、成長意欲を高めるでしょう。逆に、完璧な解決策が提示されなかった場合でも、その点を認めることで、下の者の自信が揺るがないようにします。そうでないと、下の者はもう二度と意見を言わなくなるかもしれません。半ば認めてやるだけの姿勢は、見かけ上は良いように思えるかもしれませんが、結果的に下の者の心を抑えつけてしまうことになります。これらの状況を孟子は、「五十歩百歩の違い」と形容しています。
大臣(幹部クラス)の役割は、何より人を見極め、引き立てることであると明言しています。また、我々の仕事というのは、天から授かった仕事であり、それを成し遂げるにあたって必要ならば、将軍の意見だろうが、下の者の意見だろうが関係ない、と言っています。私は「この仕事は天がお前にやれ、と言った仕事である」と考えて日々過ごしているのですが、そう考えると、困難なことであってもやり遂げられるものです。
忠の精神で仕事に取り組む
さて、上記のようにして下の者をうまく活用し、その職務に励ませると、賢才の人が目立ってくるものです。普通の人の才知は常に同じと考えるのは、道理を知らないからです。同じ人に突然才知が生まれるわけはありませんが、ある仕事に全身を打ち込んでみれば、才知が非常によく湧き出るものです。聖人の教えによれば、「忠信」「忠恕」という「忠(まこと)」ということを重んじることが大切だと説かれています。
「忠」というのは全身を打ち込んで行うことです。そうすれば人の才知が本当に現れてくるので、聖人の道では「忠」を尊重しています。ただ忠実であるだけでは賞めるような治国の上で役立つことではありません。聖賢の教えは、何事も全身を打ち込んで行なうことなのです。 例えば剣術や馬術でも、全身を打ち込んで行なうと霊妙な作用が現れます。敵が打ち下ろす太刀の下に入り、真二つになる瞬間に、敵に勝つのがそれです。
私は幼少の頃から好んで文章を書くが、昔書いた文章を後になって見ると、「さてさて我ながら見事にしたものだ、どうしてこのように書けたのか」と思うことがあります。これが全身を打ち込んでいるからこそ起こる現象であり、物事に打ち込まなければ、その人の才知の全体が働くわけではないので、才知が十分に発揮されないのです。打ち込んでやってみれば、才知の全体が現れてくるのです。この微妙な点は、実際に経験した者でなくてはわからないものです。
こうした理由から、人の能力を見極める方法は、やはりその人を実際に使ってみることにあります。自分の使い方が良ければ、その人に才知が生まれるというわけでは決してありません。古来の歴史を考察してみると、善い人がある時期から変化していくことがあり、その反対に、何の才知もないかのようであった人が、適切に使われることで才知が現れたという事例も非常に多いです。大将となる人の職務は、まったくこの点に尽きているのです。
忠という言葉を聞くと、お上のために滅私奉公するという軍隊主義のようなイメージを持つと思います。しかし、徂徠は中途は全身で打ち込むことだと言っています。これは先に出来来た通り、仕事は将軍様のために行うのではなく、天、すなわち世の中が自分に求めているものである、という考えがあるからでしょう。そのために才知を発揮しないといけない、そのために、忠、すなわち全身で打ち込むことが大切なのです。
一癖ある人をどうするか?
癖のある人が全部優秀な人であるというわけではありませんが、一癖ある者に優れた人が多いものです。 癖のある人が名将に珍重されたことが多いのも、そのためです。聖賢の書では、これを「器(うつわ)」と言います。器というものは、例えば槍であれば突く作用ばかりで、切る作用はありません。刀であれば、切り刻む作用ばかりで、突くのにはあまり適していません。錐は尖っていて、金鎚の役目は果たしません。金鎚は尖っていないので、錐の役目は果たせないのです。すべての刃物は鞘に入れておかなければ、大きな怪我をすることがありますが、そういう危険性のあるところが、すなわちその物の「癖」です。
鞘がなくても怪我をしない刀や、先端が当たっても疵をつけない錐は、みな「癖」のないもので、その代わりに何の役にも立たないのです。この「癖」というものが、すなわち「器」なのです。だから癖のあるものでなければ、器とは言えません。器でなければ役には立たないのです。人間も同じで、人の才能や知恵が一人一人異なっているのを、器という言葉で表しています。人物を評価するのに「器量」というのも、同じ文字であり、人の才知がさまざまに異なっていることを、それぞれの方面に活用して役に立たせるという意味を持っています。これは前述した「和して同ぜず」という道理にも合致するのです。
しかし、世の中の末期になるにつれて、上に立つ人の器量が小さくなっているため、何かと不安がるような小心な考え方が強くなり、一癖ある人の中から才知ある人を選び出すことを知らず、ただ毒にも薬にもならないような人を好む傾向が強くなっています。また、万病に利く薬のような万能な人こそが本当の賢才だと考え込んで、そうした人を探し求める傾向も見られますが、実際にはそうした万能な賢才は存在しません。
そのため、現代の世の中では結局、良い人はいないと思い込むことになっています。万能丸のようだと言われる人は、いずれも底の浅い人物で、しかも誰に対してもよく調子を合わせ、誰からも善人と思われるような人です。しかし、これはまさに孔子が「郷愿(きょうがん)」(「論語」陽貨)と呼んでおられる者に相当し、何の役にも立たない存在であることを知っておく必要があります。
それゆえに、賢才というのは、一癖あるが器量のある人のことであり、そうした人物は一癖ある人の中に多く存在しているということを理解しておくべきです。もし適切に使われることができれば、本当の賢才が現れてくるでしょう。
現代では、天才というのはどこか欠けた部分があるということが良く知られています。スティーブジョブズなども元々はそうでしたね。逆に言えば、何の害も無いような人は、特に得もないというわけで、平凡な成果しか出せないというわけです。一癖あるが、器量ある人間を登用し、上手く成果を出させることが出来るのもリーダーの器量と言えます。
想えば登用すべき人材は現れる
うちには登用するべき人材などいない、と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、徂徠は家康の例などを挙げて、登用すべき人材は必ず現れると言っています。
人材は必ず現れる
老中や番頭以上の地位にある人々は、ただ人材を見つけ出すことを自己の第一の職務と認識し、そのことを昼も夜も心に留めるべきです。かつて殷の高宗は、賢人を求めて夢の中で賢人の姿を見た後、その人物を探し求めて見つけ出すことができたと伝えられています。もし本心から人材を求める気持ちがあるなら、必ず人材は現れるものであり、それは心の誠実さが天に通じ、天道が助けてくださるからに違いありません。
私たちは疑いを持つことなく、真摯に人材を求める心を持つべきです。ただし、人材を見つけ出すための本心がないのは、上の立場にある人が学問に欠け、下情や実務に疎み、自己の才知を自慢する気持ちが芽生えているからです。そのため、自分と同じ考え方をする人ばかりを求め、自分の才知だけで十分だと思い込んでいる結果、本当の人材を求める気持ちが湧かないのです。
さらに、人々が職務に身を打ち込もうとしない理由には、上と下との間に非常に隔絶が生じていることも影響しています。将軍家康公や秀忠公の時代は中々なく、家光公の時代までは、城中で番衆のいる部屋などにお出でになり、下の者と直接に交流する機会もあったと聞かれます。
しかし現在は、上の立場にいる人々と下の者との距離が遠くなり、親しみを持つ心が薄れています。また、上の立場にある人々も、自らの権威を強調する傾向があります。昔は老中や若年寄も親類や知人と気軽に話をし合い、番頭も組の者と親しく交流していたようですが、現代ではそうした姿勢が薄れています。老中や若年寄は、ただ早朝に対客を行い、面会して挨拶の言葉を述べただけで帰るだけになっているようです。しかし、対客だけではその人の才知や器量を理解することは難しいです。人を見極めるには、よくその人を知っている者の推薦や意見に頼る必要があります。かつてのように、親類や知人の推薦によって人材を見つけ出すことは、成功の可能性が高い方法であり、そのような人物が世に出ることも多かったのです。
しかし、時代の変化により、このような方法を嫌う気風が広まりつつあります。さらに、老中や番頭たちも自らを威厳づける姿勢を見せることが増えています。結果として、適切な人材を見つけ出すことができなくなっているのです。人材を発見するためには、本来の職務を理解し、親類や知人との交流を大切にし、また下の者と心を寄せ合う姿勢を持つことが重要です。それによって、真の人材を見つけることができるでしょう。
「何を探しているかを知らなければ、決して見つかることはない」というのは良く知られた格言です。どのような人物が欲しいのかを明確にイメージしなければ、その人を見つけることが出来ません。
三国志に登場する三顧の礼(劉備が諸葛亮を迎える際、三回も迎えに行った)は良く知られていますが、これも劉備が諸葛亮のような軍師が自国に必要だと熱烈に思い続けていたから諸葛亮の噂を聞くことが出来、迎え入れることが出来たのでしょう。
人情を忘れてはいけない
旗本の人々も、ただ老中や若年寄の家を訪ねて歩き、ちょっと顔を見せたばかりでは、不安であるから、その老中らの家来に縁故を求めたり、その夫人の方に取り入ったりなどする。たしかに、対客にたびたび来ていた人や、夫人の方から推薦のあった人には、老中ら自身は無意識のうちに、ひいきする気持になるものだからである。
旗本の人々は、番頭とは遠く離れ、老中や若年寄とはいっそう遠く離れ、将軍様とはさらに遠く隔絶しているのであるから、下の者の気持として、上の者から隔たっていると、お互いの間で仲間を結ぶのが人情の常である。老中・若年寄・番頭らの権威は強く、たまたま意見を申し出てみても取り上げられず、何事につけても上の人の指図で使われ、自己の才知を発揮する機会がないのであるから、武士たちの気風が、みな寝入ってしまって、気持に励みが出ず、一身の安全だけをはかろうとするようになり、現在では下の者は下の者だけで団結して、武士たちの心が一般に非常に横着になっている。
すべて上に立つ人が一言でも言葉をかけてやれば、下の者はそれに感激して、命を捨てたり、職務に精励したりするのが、人情の常であるのに、上に立つ人のやり方が世の風俗につれて悪くなったものだから、武士の間に競争心がなくなり、今では器量のある人がいなくなってしまったが、これも上に立つ者の人の使い方が悪いからである。その原因は、老中や若年寄を家柄ばかりによって任命して、上と下との差別を明確にしたため、自然に上の役人が高慢になって、こういう結果を招いたのである。
老中や若年寄は、もっぱら人材を見出すことをご奉公の第一と信じ、下の者に指図をしたり押えつけたりせず、話しかけて人を使い、少々の失敗は咎めず、功績のある者は賞めてやり、器量のある人が幾人でも現われてくるであろう。政務は将軍様のお考えにそって運営されるであろう。
最近はリモートワークが進んで、上司部下の関係性が希薄になっているともいわれています。上司と関係性を深める前に辞めてしまう新人も多いようです。そうならないためには、一言でも言葉をかけてやる、つまり、人情を忘れてはならないのです。
分け隔てなく接し、人材を探した家康
人々は細かなことに気を取られる傾向が強まり、大きな利益をもたらす重要なことが忘れ去られてしまっています。この点で、家康公の大志とは明らかに異なるものです。
もちろん、家康公の偉業には多くの感銘を受けます。彼は老中の方々から番頭や物頭、諸役人までを呼び寄せ、時には軽い身分の者までもお招きになります。それは、ご政務に関する重要な問題を相談するためであったり、彼らの先祖についての話をするためであったり、あるいは御酒を振る舞ったり、お庭の石を見せて見せろと仰ったりと、様々です。その方々を冗談で笑わせることもありますし、真剣に退出させることもあるのです。何とも規則のないように思われる行動ではありますが、「最初は小身の大名でおありになったのが、天下を支配するようになられたので、お行儀はよく知っておられないのだ」と、些細に批評する者もいるものの、私はただ大変におおらかな御姿を拝しています。
家康公がこのような平民的な態度を取られていたことから、旗本の人々が低い身分の者まで、彼によく親しまれることとなったのも納得できることです。
歴史上、自分に従順で、良いことしか言わない家臣だけを身近に置いている君主は、必ずと言っていいほど没落しています。これは会社経営者もよく注意をしないといけない点でしょう。
諸役人の勤務に暇があるようにすべきこと
すべての役人は時間に余裕があるべきでございます。特に責任の重い地位にあるほど、むしろ暇を持つようにしなくてはなりません。老中や若年寄のような要職の者たちは、国政全体を取り仕切る重責を担うため、社会の隙間に気を配り、細部に注意し、さまざまなことを熟考し、時折各役人を呼び寄せ、彼らの様子を見守り、仕事を遂行できるよう支援することが肝要なのです。上に仕える心意気を持てば、他者の評価には気を使う必要はございません。
かつて、京都所司代を務めた板倉周防守が江戸に向かう際、松平伊豆守が「将軍様がようやく政務に心を注がれるようになっておられるようです。上方の情勢についても詳しくお聞きになりたいと思っておられるので、今後は私たちに送ってくださる書状を、もう少し丁寧に書いて情勢を将軍様にお伝えするようにしてはいかがでしょうか」と述べました。
しかし、周防守は次のように答えました。「百二十里も遠く離れた場所で、久しぶりのことに当たるものです。そのために私が派遣されているのです」と。彼は将軍様に理解されることはないと思いながらも、身を打ち込んで勤勉な職務を果たしているとおっしゃり、将軍様が大変喜ばれたとのことです。周防守が送ってくる書状には、常に将軍様の機嫌を伺い、「朝廷の状況に変化はありません」と簡潔に書き、「恐れ多くも申し上げます」と結んで、何事も伝えずにおられたと聞いております。今の時代でも、重要な役職に就く人々が少なくとも周防守の半分の器量があったら、その気風が一般の人々にも伝わり、「こういう考え方なのだ」と感じられるでしょう。
現代の役人たちも老中をはじめ、すべての役職者が、あらゆる事柄において余裕を持つことが大切です。統治という仕事を夢に見ることも考えることもないようではなりません。これらの人々には、職務に身を打ち込む余裕が必要なのです。その上で誤りがあるように見せかけるならば、彼らの考え方も深まり、「統治」ということを理解できるようになることでしょう。
老中、若年寄、物頭、寺社奉行、町奉行、勘定奉行、代官などは、それぞれ彼らが統治する領域や部下の中で、悪人が多く出現し、風紀が悪化している場合、それはすべて彼ら管理者の責任です。統治とは、単に下の者の違反を取り締まるだけのことではなく、下の者を教育し、訓練し、悪人が出ないようにし、風紀を改善することが求められるのです。役人たちが統治の道を歩むためには、単に裁決を下すだけでなく、下の者を他人ではなく仲間として見る心を持つことが重要です。また下の者の法規違反を取り締まることだけを治めと思っているのは、下の者を敵と見て対抗するような気持ちであるから、それでは人の頭となり、人の支配をする道に反することになるのである。
ここに書かれていることは、まさに私たちが普段、経営者向けにご支援していることと同じです。私たちは仕組み化を通じて、社長がこまごまとした仕事や現場の仕事に忙殺されないようにするご支援をしています。経営者の自由時間は計り知れないほど価値を持ちます。経営者が暇を作り、その時間でより大局的な視点で組織を見たり、次の事業を創るのです。それが永続的な会社を創るために欠かせないことです。
本当の治めとは彼らの強みを活かせるように人材を登用すること
本当の「治め」とは、自分が支配する領域や配下の者たちが主君から任されていることを意識し、末端の者までも見捨てることは許されないという大切な考え方です。役人たちは、聖人の道である「民の父母」という姿勢や、朱子学の儒者が説く「仁の道」といったものを心に留めております。
ただし、憐れむことや慈悲を示すだけでなく、信義を守り、道理に基づいて物事を処理することも重要です。例えば、父母が子を育てる際には叱りつけることもあれば、厳しくしつけることもあり、時にはだますこともあります。同様に、役人が下の者に対して処罰したり、だましたりすることもあるかもしれません。
要は、世話をよくして、心をかけて、下の者たちの生活が円滑に運ぶように尽くすことが「仁」なのです。したがって、「治め」を実行しているかどうかは、見えないものであり、時間が経過することでその治め方が評価されるのです。したがって、役職に就いた者は職務に心を入れ、外見や外聞にはこだわらないことが求められます。
板倉周防守は、役職に心を入れた人物であったため、「治め」に気が付いていた人物として伝えられております。京都の住民が、個々に自分の職務を果たす限りにおいて、京都の町は治まると言われるほどでございます。公家は和歌を詠んだり学問をし、少々の悪いことがあっても許されると聞いております。医者は治療を良くし、職人はその家の職業を勤めることで少しの過失が許されたとも言われています。
ある時、周防守が京都の中の田舎へ行ったところが古い神社で、建物も壊れているのに、神主は古びた装束を着て、拝殿で本を読んでいるのを聞いたところ、「神道の本でございます。」と答えた。1年後、同じことを尋ねると、「一年前と変わりがありません。」と神主が答えた。
周防守は感心して、「この神社の修復は、幕府から出費してもらうことは困難であるから、自分の家で修復してあげよう」と言って、修復してやったという。これも神主が家業たる神道の学問を大切にしていたのを賞めてのことで、京都を治めるということに一身を打ち込んでいたからである。
今でも右の神社は、板倉家の費用で修復することになっているという。これを世間によくある慣例と同じように思い込んで、後任の神主も当然のように願い出し、板倉家の子孫も周防守の本来の意図を知らずに、ただ先祖がこの神社を信仰したためだと思っているのは、残念なことである。一体に世間でも、周防守といえば名裁判官とだけ語り伝えているのは、今の世の人々に本当に人物を知る目もなく耳もないことを示すものであろう。
これが政談の第三部の最後になりますが、とても大事なことが書かれていますね。人々が自分の強みを活かせる仕事に就くことで、世の中が発展していくと同時に、人々の心が安らかになる。それが「治める」ということです。治める者は天から預かった役割を全うするため、慈悲の心を持ちながら、時に厳しく指導もしないといけないと書かれています。まさに組織を運営するものにとって格言と言えます。
まとめ:徳を身に付け、仕組みで治める
以上、人材登用についての徂徠の思想をご紹介してきました。300年経った今でも通用する(というか、多くの人はここに書かれている基本的なことを理解していない)文章を書いたことは本当に驚かされます。
徂徠は儒学者であるため、徳を重視した統治を志向しているように見えます。現代のビジネス社会では、経営リーダーが人徳を身に付け、その人徳に基づいた利他の心で、顧客の役に立つ仕組み、社員が活躍し、心穏やかに仕事が出来る仕組みを作っていくことが大切かと思います。
仕組み経営では、そのような経営の仕組み化を行い、永続する会社づくりをご支援しています。詳しくは以下の仕組み化ガイドブックをダウンロードしてご覧ください。